Your are here: Home // Archives for 9月, 2010
研究室配属に関するお知らせ
地域環境に配慮した運動施設の設計提案
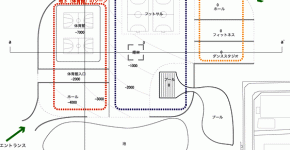
この提案では中野区警察大学跡地を敷地として公園と一体となった運動施設を計画します. 地球規模の大きな環境よりも,建築が影響を及ぼしやすいある程度の範囲を地域と呼び,そこへ建築が還元出来る様な施設を考えたいと思っています.この設計提案の主な要点を以下に挙げると, 1.意匠分野と設備環境分野との連携による設計手法の試み 2.環境負荷を低減する為の設計手法 3.地域に開かれた建築の研究 であると考えています.特に 1.では環境の酒井研究室に環境シュミレーションをお願いして,設計に活かしたいと考えています. 現在の設計状況ですが,大変遅れた末,やっと原型を作り始めました. この案では,大きな敷地を西から地下のゾーン,半外部のゾーン,室のゾーンと分け, 半外部のゾーンを南北に大きく開放する事で,自然換気,通風を促す事を狙いとし...
OB会が開催されました

建築の反重力的表現に関する研究
B4の鈴木です。遅くなってしまいました。 僕が前期の論文で扱ったテーマは反重力的な建築です。 反重力的というのは、本来地球には重力が存在しているのにも関わらずそれに逆らっているかのような形態のものを指します。 こういった建築を比較したり考察することにより、建築が反重力的形態をもつ必要性はどこにあるのか、それを明らかにすることを目的としました。 装飾の時代が終わり、建築の興味がボリュームの操作や形態にシフトしてきた20世紀初頭あたりから建築は反重力的表現を用いるようになります。 特にロシア構成主義では、計画、実作に関わらず新たな形態を模索していて、そこが出発点であったと僕は考えています。 時代を追って行くと、反重力的形態が生まれたあたりでは、主に思想の反映や、何かを象徴するものとして用いられました。その後から今に至る流れでは主に空間の操作のために...
柱による空間生成に関する研究

B4の齋藤です。投稿に苦戦しました。 自分は前期に柱によって生成される空間の質に関して研究してきました。 この研究テーマを選択した理由として、 ・建築の成り立ちを考えるために主要構造部に焦点を当てることが必要であること ・古代建築から近代建築までの建築技術の進化に伴い、柱の必要性、空間での在り方、構造デザインなどあらゆる領域で思考することが可能になったこと が挙げられます。 本研究では空間生成に焦点をあてたため、柱の意味論や象徴性といった主観的な見方は必要最低限に絞っています。 研究の概要としては、 1、柱(単独)のキャラクター 2、柱(群)の配置(場の生成) 3、柱にまつわる思想 と章立てて、1では「形状・プロポーション」、「様式・意匠」に分け、2では「領域性」、「方向性」、「中心性」と分類し特性を研究しました。 3ではコルビュジエに代表される「ピロティ柱」、建築全体に影響を及ぼす「1本...
建築におけるルーフの領域性に関する研究

B4の木村です。更新遅くなりました(ひぃー;°Д°) 私は前期の論文で、建築のルーフの領域性について研究しました。 建築単体においてルーフがどのような意匠になっているのか、またそれが空間にどのような影響を与えているかを考察し、まとめました。 主な論点はルーフと空間の対応関係についてです。 ルーフが形成する領域について考えるにあたり、ルーフの形態が空間に及ぼす影響、すなわちルーフと空間の対応関係について考え、分析しました。その対応関係は一般的に以下の3つに大別できるとして、それらを筋にいろいろ考えました。 1.ルーフによる領域指定 2. ルーフによる領域分割 3.ルーフによる領域統合 ルーフによる領域指定では、ルーフは根源的に覆うという操作から成り立ち、その投影面がルーフの形成する領域ですよというお話です。さらにその中で、半屋外空間な...
2010年度日本建築学会大会(北陸)
上海の調査が終わりました

皆さん、こんばんは。 今杭州の空港で飛行機を待っています。 9月2日から4日までの三日間で、上海の新型里弄住宅を調査しました。ヒヤリングの役割なので、できる限り写真を撮りましたが、自分が持っている資料はまだ十分ではなく、また合同調査の方に資料がもらえるように頼みます。次回写真をアップロードします。 5日に森ビルの上海国際金融中心を見学して、6日に万博に行きました。人が多くて、国家館はただイギリス館に入りましたが、それだけ見れば十分だというような気がします。また、中国のいろんな企業館、特に建築事業やディベロッパの展示を見ました。「万科」という中国のディベロッパの館は建築自体と展示がとてもよかったと思います。 その後二日間で、杭州に行って、見学と旅行をしました。 北京に着き次第、北京の調査と資料収集を始めます。あっという間で夏休みが半分しかないんですが、これから急いで頑張ります。 それでは。 ...
ジャン・プルーヴェのアルミニウムを用いた作品の分析と考察
M2佐藤あかねです。 1)伊東豊雄:ブルージュ・パビリオン(2002)、2)難波和彦+界工作舍:箱の家83(2004) 2002年5月、建築基準法が改正され、アルミニウムに構造材としての役割が認められました。以降、アルミ建築は日本では伊東豊雄さんや難波和彦さんなどが積極的に取り入れていますが、まだ一般的な普及に至ってはおらず、実験段階にあります。アルミニウムは軽量で耐蝕性に優れ、容易にリサイクルできるという特性があり、環境に優しい素材として注目されています。これからの環境時代を築く上でアルミ建築の果たす役割は大きく、研究の意義があると思っています。 ...
空間の分節と接続の多様性と両義性について
B4の大谷です。 僕は前期を通して、空間構成の際の〈分節〉と〈接続〉という操作と、その結果生み出される空間の状態についての研究を行いました。 本論では大きく分けて、 1.分節と接続の変遷 2.分節と接続の多様性 3.分節と接続の両義性 の3つについて述べました。 ここでは、どのように研究を行ったかを述べたいと思います。 まず、日本民家における可動間仕切りとユニバーサルスペースという過去の2つの手法を例示し、分節と接続による空間構成手法の現代的な特徴は、「平衡状態的な両義性」にあることを示しました。 可動間仕切りは分節と接続の可変性を、ユニバーサルスペースはそのどちらも意図しない普遍性を意図しているのに対し、現代はそのどちらをも意図するような状態を追及しているといえます。 その結果、分節と接続という手法は多様化してゆき、さら...

