You are here: Home // PROJECT&RESEARCH
ミクロな店舗群による商業地の形成過程に関する研究-中目黒・代官山・原宿をケーススタディとして-

修士2年の増井裕太です。2014年08月23日時点での修士論文の中間報告を掲載します。 0.序章 0-1.研究の背景 東京の中で、かつては木造の戸建て住宅やアパートが建ち並んでいた簡素な住宅地であったが、バブル崩壊以降(1990年以降)に商業化しているエリアが見られる。それらのエリアは、大規模再開発により小さな敷地を集めて大きな敷地として新たに開発するのではなく、敷地の大きさは変わらずに小さな(ミクロ)な店舗により商業地が形成されることで、都市の更新が成されている。本エリアを実際に歩いてみると、建物のビルディングタイプは変えずに用途を変更して、店舗として利用している事例が多く見られることから、店舗の発生には周囲の大規模再開発や店舗の開業などから何らかの影響を受けているのではないか。 0-2.研究の目的 大規模再開発とは異なるミクロな店舗により商業地が形成されていく過程(プロセス)を追うこと...
「Timberize TOKYO 2020」展
町工場の立面構成に関する研究 〜大阪府東大阪市における町工場集積地域を対象として〜
B4田島です。大変遅くなり、申し訳ありません。夏合宿での前期論文を投稿します。 1.序論 1-1.研究の背景 大阪府東大阪市は、日本でも有数の工業都市として知られている。工場数は全国4位となる6016箇所あり、工場密度においては東京都や大阪市をしのぎ全国1位である。東大阪市では、特に製造業において、有機的な分業システムと地域間ネットワークを構築しており、下請けのみならず横請けという仲間同士が気軽に連携する企業間取引が有効的に機能している。しかし近年、経済構造の大きな変化によって、事業所数や従業者数、製品出荷額の減少傾向にあり(図1)、分業システムやネットワークの崩壊、産業空洞化が懸念されている。さらに、製造業に対する若年労働力の不足や従業員の高齢化、後継者不足といった問題が挙げられている。 図1 事業所数(青軸) 従業者数(茶軸) 1-2.研究の目的 このような現状の東大阪市の町工場におい...
間伐材ブロックを用いた住空間の間仕切り壁の設計

B4の柏木です。前期研究について投稿します。 1.1研究の背景 技術の進歩と共に建築の分野で用いられる材料は多様化してきた。環境問題が叫ばれる現代において自然資源の利用は重要だが、木材に関して目を向けてみると安価に入手できる輸入材が市場の多くを占めており、国産材の流通は減り日本の林業は衰退している。人工林において間伐は樹木の育成や土砂災害防止のために必要不可欠な作業であるが間伐材の値段に対して間伐にかかる費用が大きいため間伐をすると赤字になることから間伐を行わず放置された人工林が増え、日本の森林の荒廃が問題となっている。さらに従事者の高齢化・減少により過疎化される山村も増えてきている。しかし、日本の人工林は高度経済成長期におきた造林ブーム時に植えた人工林の伐採期を迎えており、平成22年には「公共建築物等における木材利用促進法」が施行され、平成20年に施行された「間伐等特措法」...
吉祥寺駅北口サンロード商店街・ダイヤ街商店街におけるアーケードの形成過程についての研究
B4の崎山です。夏季に発表を行った論文について簡単に記述させていただきます。 1.序論 1-1.研究の背景 吉祥寺駅北口には複数の商店街が存在している。その商店街の内、サンロード商店街とダイヤ街の2つの商店街にはアーケードが架かっており、このエリア一帯を領域づける役割を果たしている。 古くからの店がまだ多く存在する商店街を衰退化させることなく成長させてきたアーケードは、今や全国的に数少ないものとなっており、サンロードとダイヤ街は活性化しているアーケード商店街としては貴重な存在である。また、アーケードの有用性が疑われる中で、この2つのアーケードは吉祥寺駅北口の重要なシンボルとなっており、無くてはならない存在として認識されている。そして開閉式天井が用いられているところから、単に屋根や天井としての役割をアーケードに見出している訳では無いことがわかる。アーケードによる都市空間の室内化...
商店参道における社寺要素に関する研究

B4丹波です。2013年前期に行った研究について投稿します。 1. 研究の背景 社寺の敷地の外から境内へと続く参道は、神聖さを高揚させる空間である。境内地の外の参道は一般市街地に展開するが、なかには参道の両側に商店が建てられた境外参道がある。それらは商店街という空間を生みだし、社寺へと続く参道に新たな価値を付加している。 境外参道に商店が加わることで、景観の要素は街路樹、舗装面、街灯などの他に素材、構成部材、色といった建築物の要素も含まれる。さらに地形や参道の形状によって、参道を進む際に見える要素は変化する。人は空間を認識する際、これらの様々な構成要素を視覚から取り込み、景観として捉えていると考えられる。商店を有する参道( 以下、商店参道) は、商店を有さない参道に比べ構成要素が多く、さらに視覚だけでなく聴覚や嗅覚も働く。商店の要素が強いが故に、空間を参道として認識するよりも...
ルイス・カーンの光の設計手法について―ミクヴェ・イスラエル・シナゴーグにおけるケーススタディ―
1.序論 1-1.研究の目的と背景 ミカベ・イスラエル・シナゴーグは11年もの歳月をかけて設計されたが、建設には至らなかった。しかし、この作品はカーンの作品の中で重要な意味を占める作品だと考えられる。そこで、この作品を研究し、3D化することで、採光のシュミレーションを行い、カーンの設計手法の意図を読み取る。 2.ミカベ・イスラエル・シナゴーグの概要 ミカベ・イスラエル・シナゴーグのプロジェクトは1961年5月に始まり、それから7回のスタディ案の変更を経て1963年10月29日に最終案が決定した。 しかし、度重なる設計変更に伴う予算の増額により、その結果深刻な資金不足となり建設工事が始まることはなかった。 敷地はカーンの生まれ故郷であるフィラデルフィアで、カーンはユダヤ系の哲学者の血を引くことからユダヤ教の教えである「生命の木」をプランに反映させたと考えられる。 3.スタディ過程の分析 3-...
Louis I Kahnのアンビルド作品における光の設計手法の研究 -3Dモデルによる光の復元-

修士2年の新谷です。 前回の投稿から、夏合宿までの成果を投稿します。 前回、カーンの開口部のカテゴリーに関して述べた。カーンの作品(アンビルドを含む)の中でも採光が特徴的であるものを表にしてまとめた。 この表から、カーンのアンビルドにおいて重要な物(カーンの採光において節目となったものや建てられた物に影響を与えたもの)であると思われる作品を選定し、今後の研究対象とすることにした。 1.合衆国領事館および公邸 この作品は、ガラス面の手前に自立する日よけの壁と、日よけの屋根が複合して使用されている。アンゴラでの強い日差しを遮るために、当時カーンはこの日よけ屋根が最高の解決方法だとしていたが、この後強い日差しで設計する機会が多くあったが、この日よけ屋根が再び用いられることはなかった。初期のカーンに多用されていた直接日差しを遮る光の制御方法と、二重壁が組み合わせて使用されていること...
秋葉原における電子機器・部品街の空間特性に関する研究
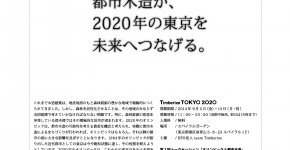
B4の長谷川です。 前期の研究内容について投稿します。 ■序章 研究の背景と目的 0.1 研究の背景 秋葉原は第二次世界大戦後、技術的な兵役についていた復員兵による電子機器・部品を取り扱う露店商が、焼け野原の秋葉原に発生し始めた。その数は電機工業大学(現東京電機大学)に近い立地から次々と増え始め、街を形成するに至る。しかし、1949年(昭和24年)のGHQによる露店撤廃令により、これらの露店商は秋葉原駅のガード下に収容されるようになった。その際に組合単位でビルが設立され、そこに露店が収容される形で、現在の秋葉原の電子機器・部品街が形成されている。戦後から現在に至るまで、秋葉原は日本随一の電気街として、またオタク文化発祥の地として、他に類を見ない発展を遂げてきたことは言うまでもない。そのような発展の原点に位置付けられるのが電子機器・部品街の活躍であり、長い歴史のもと、貴重な固有な風景として現...
環境装置としてのアトリウムについて ―現代のオフィスを対象として―
B4の釣井です。 前期の研究を報告します。 1.序論 1.1.研究の背景 建築分野において資源やエネルギーの消費で排出する二酸化炭素の割合は産業分野が排出する割合の約40%である。これは、建築において資源やエネルギー消費などは環境負荷が大きいので環境配慮など社会に要求される義務を果たさなければならない。 技術の加速的な発展が20世紀の大量生産や大量消費を促進した。1987年に国連のブルントランド委員会が発表した「我ら共有の未来」の中で「サスティナブル・ディベロップメント」の言葉1)を用いた。それ以来サスティナビリティの概念は20世紀末葉の最も重要なパラダイムの一つになった。そして、2002年には建築環境・省エネルギー機構がCABEE(Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency)と呼ばれる建築物の...

